誰もが簡単に登れてしまう山、それが富士山。
しかし、3,000mを遥かに越える山であるがゆえの高山病との闘い、遮るものが無く遠くまで見通せるがゆえになかなか近づいてこない山頂、上りは上るだけ下りは下るだけと明確である半面単調なこと、天候の急変、そして自分との闘い。。。
日本一高い山は、やはり日本一困難な山なのです。そして、それを克服したときの満足感、登った人にだけ見ることが許される、神々しいまでのご来光。登るしかないでしょう!!

富士登山事前準備
段取り八分は富士登山のためにあるようなもの。体力作りも含めて事前の準備は入念にしましょう。
あとは本番での気力と体力だけ。
装備一覧
| 絶対に必要な装備 | あると重宝する装備 | お好みで |
| ザック | 帽子 | カメラ |
| 靴 | 食料 | 双眼鏡 |
| 靴下 | サングラス | 筆記用具 |
| ウエア | 日焼け止め | メモ帳 |
| レインウエア | スパッツ | ハガキ(記念に山頂で出す) |
| タオル | 杖(トレッキングポール) | |
| 飲料水 | ホカロン | |
| ライト(夜間登山) | 携帯酸素 | |
| 手袋(軍手) | 携帯電話 | |
| 現金 | トイレットペーパー | |
| 健康保険証のコピー | ||
| ビニール袋 |
装備解説
ここでは上記「装備一覧」の解説をします。
- ザック
 25~30リットル程度の大きさがあれば大丈夫でしょうが、携行する装備によってはもっと大きなものが必要かも。。。また、雨対策にザックカバーも必要。ザックをスッポリ覆えるビニール袋でも良い。
25~30リットル程度の大きさがあれば大丈夫でしょうが、携行する装備によってはもっと大きなものが必要かも。。。また、雨対策にザックカバーも必要。ザックをスッポリ覆えるビニール袋でも良い。 - 靴
登山・トレッキング用の靴が望ましいです。スニーカーにしても靴底のしっかりした、最低踝近くまで高さのあるものにしましょう。 これから購入するならば、透湿防水性能の優れたゴアテックスのものがお勧めです。靴の外にGORE-TEXと書かれたプレート等が貼り付けられているのですぐわかるはず。
これから購入するならば、透湿防水性能の優れたゴアテックスのものがお勧めです。靴の外にGORE-TEXと書かれたプレート等が貼り付けられているのですぐわかるはず。
私は富士登山用に三島の東京靴流通センター(全国各地にあるようです)で税込み1万円ほどのゴアテックスのものを買いました。ヨーカドーにも別メーカーの同様の製品がありました。
サイズは靴ひもをしっかりと結び、爪先をトントンとやって指先が当たらず、踵に人差し指一本入る程度の余裕があること。できれば実際に履く靴下を持って行って確認しましょう。 - 靴下
綿はダメ!!ですが、速乾性を謳っているものならば大丈夫かも。。。
購入するならクッション性も考慮して、トレッキング用などの厚手のものにしましょう。日常の靴下を2枚履くってのもありです。(年配者には1枚ではクッション性が心許ないので) - ウエア
靴下と同じで、とにかく綿は止めておきましょう(これも、速乾性を謳っていれば大丈夫かも知れないが)。汗や雨で濡れたとき気持ち悪い、重い、乾きが遅いの三重苦です。ジャージが一番。
そして薄手のものを重ね着するのが基本。
上半身・・・半袖のTシャツ、長袖のシャツ、防寒着インナー(薄手のフリースやセーター)、防寒着アウター(ジャケットやヤッケなど防風性のもの、レインウエアで代替え可)
下半身・・・下着、ズボン、防寒着アウター(レインウエアで代替え可)
ザックの大きさに制限されるので良く吟味しましょう。
個人差はあるが、これで寒くて我慢できないようなら日中天気の良いときに登りましょう。山頂のご来光直前の気温は5℃前後と、東京の真冬の日中と同じくらいでしょう。 - レインウエア
ゴアテックスの本格的な登山用のレインウエアを勧めたいところですが、かなり高価(上下2万円以上)です。ふところに余裕があれば買ってください。ゴアテックスでなくても、透湿防水性能であればいいでしょう。ネットを調べると6,000円位からありそう。できれば上下セパレートタイプいい。街中で着るようなコートやポンチョタイプは役に立たないです(経験済み)。無ければしょうがないが。。。
必ず使うというわけでもないので、悩ましいところです。 - タオル
普通のタオルで良いので、汗拭き用に1枚、非常用に1枚の最低2枚は準備しましょう。
下山時の砂埃除けにも使えますし、帽子代わりに姉さんかぶりもいいでしょう。 - 飲料水
市販のペットボトルなら、500mlを2本くらいは必要かも。水、スポーツ飲料などお好みで。私はポカリスエット一筋。
山小屋でも売っているし、山頂には自販機もあるが、とにかく高い。 - ライト
ヘッドランプなら最高。普通の懐中電灯でも良いが、小型で軽いものにしましょう。予備の電池も忘れずに。 - 手袋(軍手)
登山用が望ましいが、滑り止めの付いた軍手でも良い。 - 現金
最低1万円程度(千円札で)と100円硬貨を10枚ほど。。。
トイレはすべて有料(200円か300円)。また、万一山小屋(だいたい素泊まり6,000円前後)にお世話になったときのために。 - ビニール袋
ゴミ袋です。コンビニ袋でも良い。また、ザックの中身はすべてビニール袋に入れて万一の雨天の水の浸入に備える。 - 帽子
日差し避けにつばの有るもの。富士山は樹林帯がほとんどないので、日中はもろに日差しが当たります。
寒がりの人には防寒用の毛糸の帽子も必要でしょう。 - 食料
出発前に食事は取るにしても、途中で結構腹が空くのです。
おにぎりやお菓子、飴、チョコレートなどを携帯すると良いでしょう。記念に小屋で食事もいいですが、高いです。  サングラス
サングラス
天気が良いと遮るものなし。つばのある帽子とセットで。- スパッツ
小石の靴への侵入防止。雨のときは水の浸入も防ぐ。 - 杖(トレッキングポール)
富士登山名物(?)の金剛杖(1,000円だったかな)を買って、焼き印を捺してもらうのも良い記念になる。
強風のときや下りで重宝。 - 携帯酸素
吸っている間はさすがに効きますが、気休め程度かも。。。 - トイレットペーパー
芯を抜いて、必要量携行。ティッシュは溶け難いのでダメ(持って帰るのなら良いが)。
体力作り
階段またはイスの昇り降りが良い。つまり太ももを鍛えるということなので、ウォーキングはあまり有効とはいえない。やらないよりはましだけど。。。
どのくらいやるかは個人差はあるが、太ももにやや疲労を感じるくらいとし(無理はしない)、本番の2日前くらいには止めて筋肉を休ませましょう。
富士山の登り方
富士山が他の山と違うのは、標高が日本一、登りはひたすら登り、下りはひたすら下る、強い陽射しを遮る樹木がないことなど。これらが原因で、高山病になりやすく、気がゆるみやすく、体力を消耗しやすいこと。
服装
出発時は少し肌寒いくらいの服装が良い。
山小屋で一泊を前提にすると、出発は午後4時頃で、気温は20℃前後と思われるが、半袖のTシャツ1枚で十分です。気温に合った服装をして出発すると、たちまち大汗をかくことになるでしょう。
とは言っても個人差があるので、歩いていて軽く汗ばむ位を目安にしましょう。
ただし、休憩時は体を冷やさないように防寒着を着ましょう。
私の場合は半袖のTシャツとコンバーチブルのパンツの下を外してスタートし、途中で長袖を1枚羽織り、パンツの下を追加。そのまま小屋泊まり。翌早朝の出発時は上にフリースを着て、途中で上下防寒着を追加します。
呼吸と歩き方
歩き始めは誰でも元気が有り余っているが、高度を上げるにつれ呼吸も荒く足元もおぼつかなくなってくる。とにかく、ゆっくりとイーブンペースを守ることが重要で、下記の呼吸法が守れなくなってきたら、オーバーペースと思うこと。
ユックリ歩くのは体を高所に慣れさせ、高山病を予防する意味合いもあります。
- 呼吸法(腹式呼吸)
吐く方を意識し、口から1度で吐いて鼻から2度吸う、を繰り返す。
最初は肺から全ての空気を出すつもりで息を吐くこと。
高度が上がるにつれ、毎回深呼吸をするが如くに呼吸する。これが高山病の最高の対処法です。
そして歩いていないときも、意識して深く息をすること。実はこっちの方が肝心かも。。。休憩に要注意!!
それまで平気だった人が、山頂に着いて休憩しているうちに頭痛がしたり胃がムカムカしてくる(つまりは高山病)ことはよくあること。これは今まで歩くことで深く息をしていたのが、休憩で普通の呼吸になってしまったために起こる。
山小屋では高山病の対処にゴム風船を膨らませるのだそうです。つまり、大きく息を吐き大きく息を吸うということです。 - 歩き方
歩幅は半足分以下で、速さは1秒に1歩以下(呼吸に合わせる)。
通常の歩き方とは全く異なり・・・
足を踏み出す → 足裏全体を地面に平行に置くように降ろす → 下ろした足に全体重を載せる → 後ろ足を持ち上げる(爪先で蹴らないこと) → 足を踏み出す
・・・ロボットのような歩き方なのです。
大きな段差や不安定な岩は、たとえ遠回りになっても避けること。つまり、大げさな動きや踏ん張るなど足に必要以上の負担を掛けないこと。 - 目線
踏み出した足を下ろす位置に目線を持って行き、路面状態を一歩一歩確認する。
景色や地図を見たりなど、目線を外すときは安全のため立ち止まること。 - 休憩の取り方
各合目間に掛かる時間を前もって確認しておき、少なくとも1時間前後に1回休憩する。
休憩時間は5~10分程度で、体が冷えないようジャケットなどを羽織ると良い。
水分補給や呼吸を整える、ストレッチなどで次に備える。
食事を取る場合でも極力短時間で済ませる。
高度が上がると数十メートル進むごとに息が切れて座りたくなるが、絶対に座ってはいけない。この状態で座り込むと立ち上がるのがとても辛くなる。一息つくのは良いが、立ったままで、呼吸が整ったら歩き出すこと。
休憩後の歩き始めに足が重く感じるが、休憩のため老廃物が足に留まったためで、動き出せばすぐに元に戻ります。 - 水分補給
ノドが渇いてからでは遅すぎる。水分不足は高山病の一因。
休憩ごとや1時間ごとなど定期的に、2口程度補給する。がぶ飲みすると余分な水分は尿となって排出されるだけなので避ける。また、水分はぬるいより冷たいほうが体内に吸収されやすい。 - 食料補給
出発前は普通に食事(ご飯物を)を取り空腹は避ける。
登山中も極端に空腹を感じないように、ビスケットやチョコレートなど好物を持参して、適宜取るようにしましょう。
そして、メインの食事はおにぎりなど炭水化物がベストです。この炭水化物は行動中のエネルギーの元になるのです。炭水化物が足りなくなると、エネルギーが作られず疲労感が増します。これを山用語で「シャリバテ」といいます。
不思議と腹が満たされると疲れも吹き飛んでしまいます。
その他
-
場面にもよるが、登山者とすれ違ったり、追い抜くときは声を掛けましょう 2004年8月10日剣ヶ峰初登頂
2004年8月10日剣ヶ峰初登頂 - トイレは有料。徴収者が居ない場合がほとんどですが、ズルをしないで支払いましょう
- 山で残して良いのは想い出だけ。。。ゴミは必ず持ち帰りましょう
- 頑張ることは大切ですが、体調が最優先。
我慢できないほどの頭痛などになったら、無理せず下山しよう。最悪命に関わります
最後に、せっかく登る富士山です、ぜひとも最高峰の剣ヶ峰(3,776m)に立ちましょう。そして仕上げにお鉢巡りでしょう。



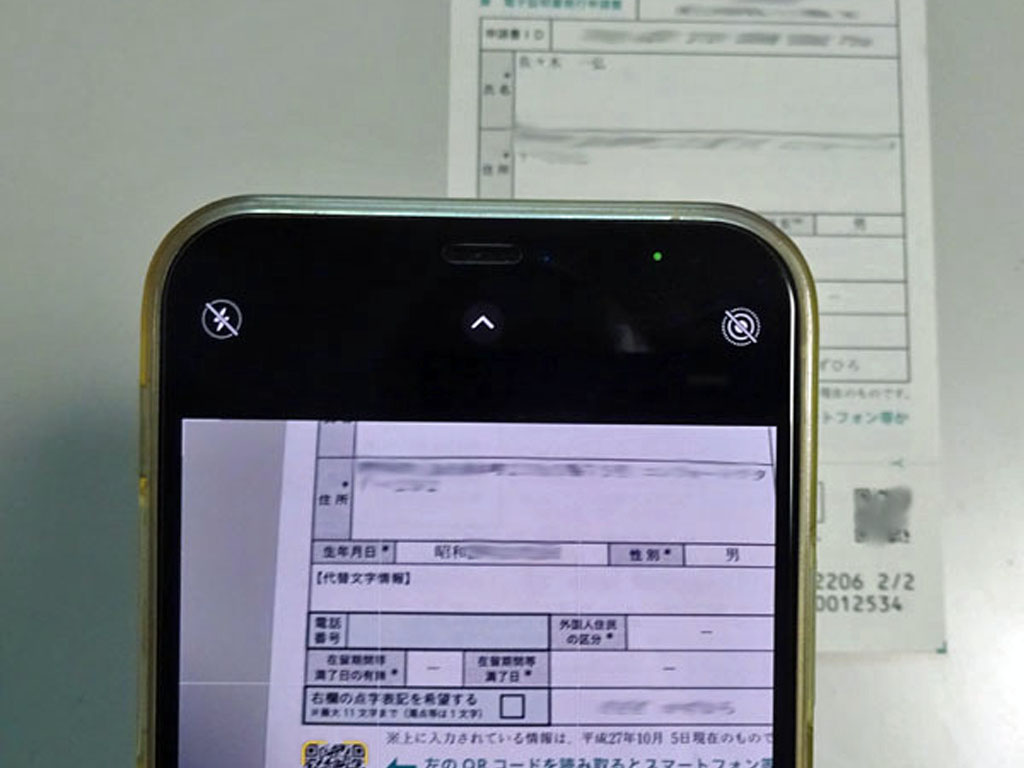
コメント